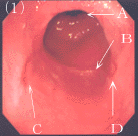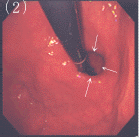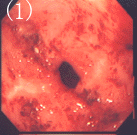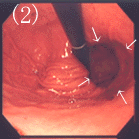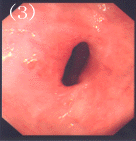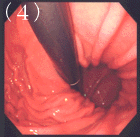がんこな胸焼け・・・逆流性食道炎増加中
逆流性食道炎は胃の酸や消化液が食道に逆流し、粘膜に傷ができて胸焼けやみぞおちの痛みなどを生ずる病気です。最近日本人に増加しています。
症状はまず何といっても胸焼けです。焼けるような感じ、胸が熱くなる、胸が重い感じ、のどの奥のほうがイガイガするなどです。胸焼けとともに多いのはゲップがよく出る、すっぱいものが上がってくる、といった症状です。人によっては気管支や肺に病気がないのにしつこい咳がでることもあります。
内視鏡検査をしてみると、食道の粘膜に浅い傷ができてビランになっています。食道の一番下(胃の入り口)の部分の粘膜の境界が胃の入り口よりも上(胸の方)にせり上がってきています。食道の傷が出来たり治ったりを繰り返すうちに傷の場所がひきつれを起こし食道が狭くなってしまう(瘢痕性狭窄)ことがあります。
当院で治療中の逆流性食道炎の患者さんの内視鏡写真です。(ご本人のご承諾をいただいて掲載しています)
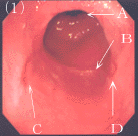 |
(1)70歳代の女性で胸焼け、みぞおちの圧迫感などがあり検査しました。食道の下端(胃の入り口の上)を観察しています。Aの黒く見えているところがが胃の入り口です。Bより手前の粘膜の色が白っぽくなっているところが本来の食道粘膜(重層扁平上皮という組織)で、これよりも奥の方の赤く見えているところが胃の粘膜(円柱上皮)です。つまり、食道と胃の境界(B)が手前(口に近い方)にはみ出ていることになります。この部分が「食道裂孔ヘルニア」−hernia:はみ出した状態の意)です。CとDの赤くなったところが逆流性食道炎による粘膜の傷(ビラン)です。 |
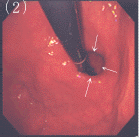 |
(2)胃の中から胃の入り口の方をふりかえってみたところです(現在の内視鏡は細くて小回りが効くのでこういった撮影も容易です)。黒い棒のように見えるものが内視鏡です。白い矢印→で示す胃の入り口が内視鏡よりもはるかに大きくなっているのがわかります。
|
2例目も70歳代の女性です。
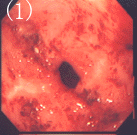 |
(1)食道の下部で出血を伴うビランがあり食道が狭くなっています。中央の黒く見えるところが食物の通り道(食道の内腔)ですが、非常に狭くなっているのが分かります。まわりに黒い血液が付着しているのは食道炎による傷から出血しているためです。このように食道が狭くなってしまうのは逆流性食道炎でもかなり進んだ状態です。
|
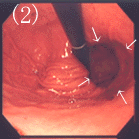 |
(2)この狭窄部を通過して胃の中から胃の入り口の方を振り返ってみたところです。白い矢印→で示したところが胃の入り口に相当しますが、本来の胃の入り口(噴門)は画面のずっと奥のほうに押し上げられています。
|
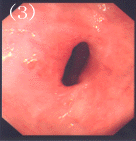 |
(3)胃酸の分泌を抑える薬で治療後の(1)の部位の内視鏡写真です。(1)の時のようなひどい炎症は治癒しています。胸焼け、つかえ感、みぞおちの痛みなどが解消し快適にすごせるようになりました。しかし、食道の狭窄はもとのままです。炎症を繰り返して瘢痕(ひきつれ)になってしまうと薬だけで元通りに広げるのは困難で、機械的に広げる治療(ブジー)が必要になる場合もあります。 |
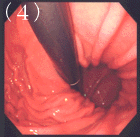 |
(4)胃の入り口は以前同様に広がったままです。胃酸が出過ぎないように抑えれば食道炎は治癒に向かうことが分かります。
|
レントゲン検査では、バリウムが食道へ容易に逆流すること、胃の境界が胸の中まで上がっていること、食道の粘膜の傷や狭窄などが分かります。この写真は上に掲げた第2例目の患者さんのレントゲン写真です。
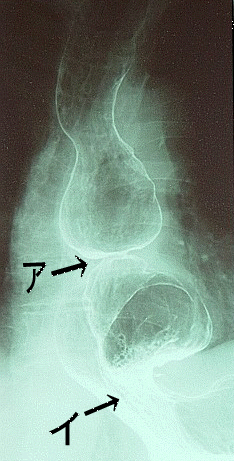 |
食道から胃の上部のレントゲン写真です。アが上の内視鏡写真で高度の狭窄を生じているところ(内視鏡写真では(1)(3)の場所)です。イは横隔膜の食道裂孔の部位で胸部と腹部の境界です。つまりイからアまで胃が胸腔にはみ出しているのです。
|
この病気になりやすい人には大きく分けて2つのグループがあります。
第一は太っている方、特に男性です。太っているとお腹の圧力(腹圧)が強くなります。するとこの圧力で胃が胸(胸腔)の方に押し出されます。胸腔と腹腔の境は横隔膜という筋肉の膜です。横隔膜に食道が通る通路(食道裂孔)があり、ここから胃の入り口の部分が胸腔に押し出されてしまう訳です。このような状態のことを食道裂孔ヘルニアといいます。それまでは食道裂孔に胃の入り口(噴門)がかかってHis(ヒス)角という構造をつくって逆流を防止しています。食道裂孔ヘルニアが生ずるとこの仕組みもうまく働かなくなります。お腹をベルトできつくしめると腹圧はいっそう高くなり食道裂孔ヘルニアもよけいひどくなります。現在日本人の男性で肥満の方がふえており、これからこの病気はさらに増加すると予想されます。
第二はご高齢の女性です。背が丸くなって前かがみの姿勢になる方が増えてきます。前かがみの姿勢になると常にお腹を圧迫している状態になります。そのためお腹の圧力(腹圧)が強くなり、やはり同じように胃の入り口の部分が胸腔に押し出されてきます。ご高齢の方は横隔膜が緩んでくるため食道裂孔も広がりやすく、食道裂孔ヘルニアが起こりやすくなります。胃袋の三分の一とか半分近くが胸の中に押し出されてしまうような高度の食道裂孔ヘルニアを起こすのはほとんどがご高齢の女性です。
さて治療はどうすればよいのでしょうか。
原理から考えれば胃酸と消化液の逆流が起きないようにすればよいことになります。
1.
日常的な注意としてはお腹をきつく閉めすぎないこと、食べ過ぎないこと、上半身を少し上げて眠ることなどです。太っている方はぜひ減量が必要です。
2.
ご高齢の方が背が丸くなるのは骨粗鬆症のため脊椎が圧迫骨折をおこしてつぶれるからです。若い頃から姿勢を良くし、更年期になったら定期的に骨粗鬆症の検査をお受けになることをお勧めします。もしその徴候があれば十分な治療をして背が曲がらないようにすることが重要です。現代の若い女性のなかには過剰なダイエット志向の人があり、若い時期の骨量が十分でないため更年期に骨粗鬆症になりやすいことが危惧されます。
3. 胃酸が出過ぎないようにおさえておけば胃の消化液の力も弱まって傷がつきにくくなります。胃潰瘍や十二指腸潰瘍の治療と同じ考え方です。胃酸が出過ぎないように抑える薬にはH2ブロッカーとプロトンポンプ阻害剤があり、これらが薬物療法の主体になっています。症状は比較的簡単に良くなり、食道の傷も治ってきますが、中止するとすぐ再発してしまいます。肥満の方がすぐ十分に減量できるとは限りませんし、曲がってしまった背骨や緩んだ横隔膜を元に戻すのは困難です。従ってこれらの薬は長期間のみ続けることになりますが、H2ブロッカーとプロトンポンプ阻害剤はともに副作用が少なく長期間安心して飲んでいただけるお薬です。
4. 逆流が起きないようにする手術(Nissen−ニッセン−手術)もあります。食道の入り口を腹腔にもどし、開き過ぎないようにしめることによって逆流を抑える手術(噴門形成術)です。この手術を腹腔鏡で行なう方法もあります。最近では、開腹せずに内視鏡で手術する方法もあります。食道の下端付近に特殊な薬剤を注射する(Enteryx法)、食道下端と胃の入り口をプラスチックのクリップで縫い付けて隆起させ胃の入り口を締める(ELGP法)、食道下端に高周波を通電して収縮させる(Stretta法)などが考案されています。食道の狭窄がひどくなってしまった場合は狭くなった食道を切除して切り取った部分を小腸でつないだり、胃を管のように形成して胸腔に引き上げて縫合するというような大手術が必要になる場合があります。このような事態にならないように予防を心がけ、早期に治療を開始する必要があります。
最初に戻る
土谷医院 TEL 0544−26−2839 FAX 0544−22−1880